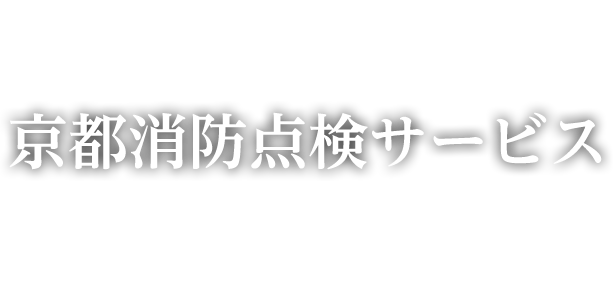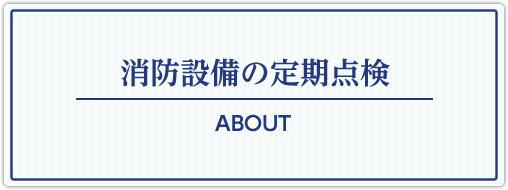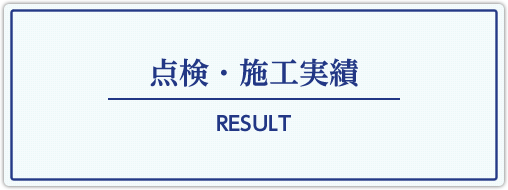無窓階!?
消防法には独自の無窓階という定義があります。
無窓階扱いになると、普通階とは別の消防設備基準が適用・・・要は厳しい基準が適用されるということです(^_^;)
漢字を読むと窓がない階・・・確かにそうなんですが、消防法上の規定では窓がない階はもちろん、窓があっても無窓階と扱われる場合があります!!
消防法における窓なしとは、避難や消防隊の進入に使えそうな窓や扉がない階を指します。
実際に無窓階か普通階になるかは、床面積や開口部の大きさや階数、さらには窓ガラスの厚み、開口部下のスペース、床からの開口部までの高さなどなど・・・細かい条件が規定されていますので、専門家である消防設備士にご相談下さい(^_^;)
実際に無窓階だった場合・・・
火災感知器の場合、普通階なら熱感知器でよかったりそもそも不要なケースでも、無窓階だと煙感知器にしなければいけない場合がありますΣ(@_@)!!
煙感知器は熱感知器より3~4倍お値段が・・・(。・ω・。)
屋内消火栓の場合、普通階なら不要な条件でも、無窓階だと設置が必要になることがありますΣ(@_@)!!
特に注意が必要なのはテナントの場合で、すでに消防設備がついている場合です
消防設備があるから大丈夫だと思っていても、用途(飲食店・宿泊施設・店舗など)によって必要な設備の基準が変わってくるので・・・
消防署へ相談に行くと・・・
「前のテナントは事務所だったんで今の消防設備で良かったんですけど、飲食店ならこの場所に火災感知器が必要ですね~」
「あ、しかも無窓階なんで、煙感知器をつけて下さいね」・・・ガーン(。・ω・。)
てなことがちょくちょく起こります(^_^;)
消防設備の改変費用が大家さんもちであれば、費用面ではまだましですが、想定外に消防設備の工事・申請・消防署の立ち会い検査がスケジュールに入ってくるので、開店時期にも影響しちゃいます(>_<)!!
消防設備は人の安全に係わる重要な設備ですので、細かい基準が法律で定められています。
建築前や入居前に、普段から消防設備に携わっている建築士さんや、専門家の消防設備士にご相談下さい(^_^)
民泊やゲストハウスを含む宿泊施設や病院・デパートなどの建築物は、その用途や規模などによって、自動火災報知器や避難梯子・誘導灯など設置義務のある消防設備があります。これらの消防設備の工事や点検・整備をおこなえる国家資格の所持者が消防設備士です。
消防設備の設置が義務付けられている建築物・規模ということは、火災のリスクが高いか、火災になった際の被害が大きくなりやすいということです。そのような施設で必要な消防設備が充足していなかったり、点検・整備ができていない場合、火災事故が発生した場合、所有者・管理者・占有者の責任が大きく問われます。
施設を利用する人々の安全を待るためにも、ご自身の身を守るためにも、法令に適した消防設備の設置・点検・整備は消防設備士の有資格者に、定期的にご相談ください (^^)
京都で消防設備の定期点検は、国家資格保持者在籍の京都消防点検サービスへ!!
<防火対象物>
防火対象物とは火災があると被害が大きくなりやすいので、ふつうの建築物より厳しく管理するように法律で定められた建築物です。
<特定防火対象物>
防火対象物の中でも、不特定多数が利用するためよりリスクが高い建物が特定防火対象物です。設備や管理にはより厳しい取り決めがあります。民泊やゲストハウスなどの宿泊施設は基本的に、特定防火対象物となります。